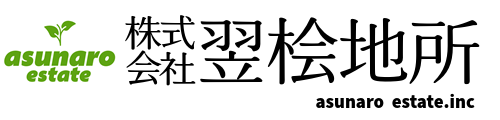なぜ再エネの電気は“捨てられて”いるのか?
――送電線の限界と、系統用蓄電池の可能性
再生可能エネルギーの導入が加速する一方で、「発電された電気が使われずに“捨てられている”」という、
少しショッキングな現実があるのをご存知でしょうか?
実は、これは再エネ導入先進地域を中心に、年々深刻化している問題です。
この記事では、その原因と解決策についてわかりやすく解説します。
「出力抑制」という現象
例えば、快晴の日。太陽光パネルはたくさんの電気を発電します。ところが、その電気が「電線に流せない」ことで、電力会社から「発電を一部止めてください」という要請が出ることがあります。
これが「出力抑制(カット)」です。
原因は“送電線の混雑”=「系統制約」
なぜ出力を抑える必要があるのでしょうか?
答えはシンプルで、「送電線に空きがない」からです。
特に、地方では太陽光発電や風力発電が集中的に設置される一方で、送電線の容量には限界があります。東京や大阪と違い、地元で使い切れない電気を都市部に送ろうとしても、送電網が“詰まって”しまうのです。
この「電気はあるのに、流せない」状態を、業界では系統制約と呼びます。
解決策としての「系統用蓄電池」
こうした系統制約の根本的な解決には時間がかかります。新たな送電線の建設には、膨大なコストと年単位の工期が必要です。
そこで、現実的かつ即効性のある解決策として注目されているのが、
🔋 系統用蓄電池(グリッドストレージ) です。
蓄電池が担うのは、次のような役割です:
- 発電量が多く、系統が混雑しているとき → 電気を一時的に「ためる」
- 需要が高まり、電力が必要なとき → ためた電気を「放電する」
つまり、系統の前に“バッファ”を設けることで、送電線の混雑を緩和し、再エネ電気の無駄を防ぐことができるのです。
「捨てられる電気」を価値に変える土地の力
このような蓄電池の設置には、
✅ 変電所に近く
✅ 広く平坦な土地
✅ 安定した電力系統エリア
といった条件を満たす適切な用地が必要です。
私たちは、そうした蓄電池用地の発掘・取得を専門に行っている会社です。
土地オーナー様、自治体様、再エネ事業者様と連携し、使われていない土地を、日本の電力安定と脱炭素社会の実現に貢献するインフラに変えるお手伝いをしています。
再生可能エネルギーは「発電するだけ」では活かしきれません。
「流せる仕組み」があってこそ、その力が最大限に発揮されます。
その鍵となるのが、系統用蓄電池。
そして、それを支えるのが、適切な用地です。
もし、
✔ 遊休地の活用方法に悩んでいる
✔ 地域の再エネ推進に関心がある
✔ 電力インフラ開発に取り組みたい
といったお考えがあれば、ぜひ私たちにご相談ください。